エコリクコラム
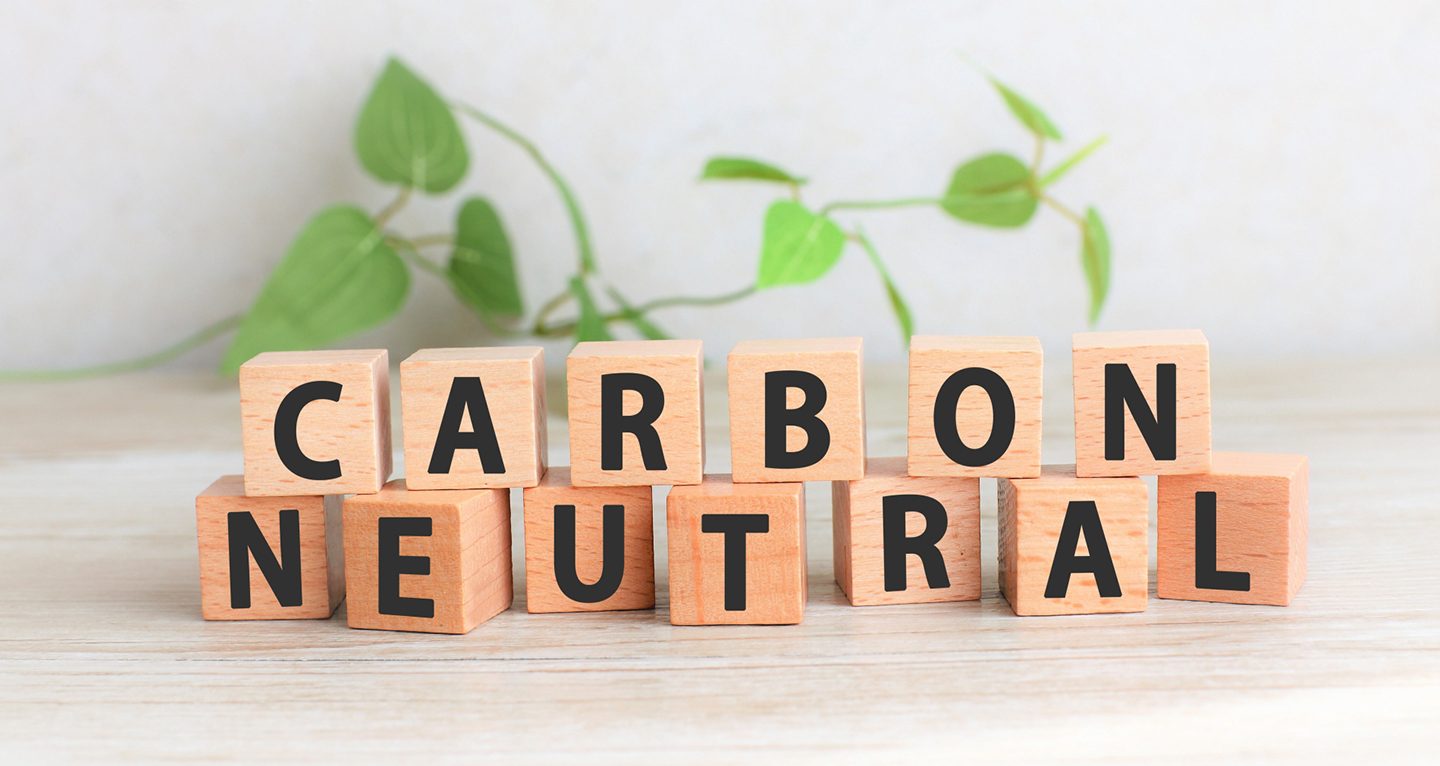
2025.5.9
トピック
カーボンニュートラルの鍵を握る!CCS・CCU・CCUS技術の最前線
地球温暖化対策が喫緊の課題となる中、CO2排出削減に向けた技術開発が加速しています。その中でも、CO2を回収・利用・貯留するCCS、CCU、CCUS技術は、カーボンニュートラルの実現に不可欠な技術として注目されています。
本記事では、これらの技術の概要、注目される背景、日本政府の政策、メリット・デメリット、具体的な事例、そして未来展望について解説します。
CCS・CCU・CCUSとは
- CCS(Carbon dioxide Capture and Storage):
- 工場や発電所などから排出されるCO2を回収し、地中深くに貯留する技術。
- CCU(Carbon dioxide Capture and Utilization):
- 回収したCO2を化学製品や燃料などに再利用する技術。
- CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage):
- CCSとCCUを組み合わせ、CO2の回収から利用・貯留までを行う技術。
注目される背景
- 地球温暖化対策の強化:
- パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標達成のため、CO2排出量の大幅削減が求められています。
- カーボンニュートラル実現への貢献:
- CCS・CCU・CCUSは、排出されたCO2を有効活用することで、カーボンニュートラルの実現に貢献します。
- 資源循環型社会への移行:
- CO2を資源として再利用することで、資源循環型社会の構築に貢献します。
日本政府によるCCS・CCU・CCUSの政策とロードマップについて
日本政府は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、CCS・CCU・CCUS技術を重要な戦略的技術と位置づけ、その開発と社会実装を積極的に推進しています。以下に、日本政府によるCCS・CCU・CCUSに関する主要な政策とロードマップについて詳細を記載します。
主要な政策とロードマップ
- カーボンリサイクル技術ロードマップ:
- CO2を資源として捉え、これを分離・回収し、多様な炭素化合物として再利用するカーボンリサイクル技術のイノベーションを加速化することを目的としています。
- 経済産業省を中心に策定され、CCU技術の推進に重点を置いています。
- CCS長期ロードマップ:
- CCS事業の計画的かつ合理的な実施により、社会コストを最小限にしつつ、日本の経済・産業の発展、エネルギーの安定供給確保、カーボンニュートラルの達成に貢献することを目的としています。
- 2030年までの事業開始を目指し、先進的なCCS事業への集中的な支援、コスト低減のための技術開発、国民理解の促進、法整備など、多岐にわたる取り組みを推進しています。
- 2050年時点で年間約1.2~2.4億tのCO2貯留を可能とすることを目標に掲げています。
- エネルギー基本計画:
- CCS・CCU技術を、鉄鋼などCO2排出が不可避な産業分野における重要な脱炭素化手段と位置づけています。
- 技術開発、コスト低減、適地開発、事業化に向けた環境整備など、長期的な視点での取り組みを推進しています。
具体的な取り組み
- 技術開発と実証実験:
- CO2分離・回収、輸送、貯留、利用に関する技術開発を支援しています。
- 国内外での実証実験を通じて、技術の有効性や安全性を検証しています。
- コスト低減:
- 技術革新や規模の経済により、CCS・CCU・CCUSのコスト低減を目指しています。
- 2050年におけるCCSのコスト目標を設定し、技術開発を推進しています。
- 法整備:
- CCS事業の実施に必要な法制度の整備を進めています。
- CO2貯留の安全性を確保するための規制や基準を策定しています。
- 国民理解の促進:
- CCS・CCU・CCUSに関する情報提供や対話を通じて、国民の理解と信頼を得るための取り組みを行っています。
- 地域ごとの説明会や情報公開などを実施しています。
- 国際連携:
- CCS・CCU・CCUSに関する国際的な技術協力や情報交換を推進しています。
- 国際的な基準や規制の策定に貢献しています。
これらの政策とロードマップに基づき、日本政府はCCS・CCU・CCUS技術の開発と社会実装を積極的に推進しており、カーボンニュートラルの実現に貢献することを目指しています。
CCS・CCU・CCUSのメリット、デメリット、課題について
- メリット:
- CO2排出量の大幅削減
- 資源の有効活用
- 新たな産業創出
- デメリット:
- 導入コストの高さ
- 技術的な課題
- 安全性への懸念
- 課題:
- コスト削減
- 技術の高度化
- 社会的受容性の向上
CCUで生産される主な物質と具体的な事例
1)日本国内:
日本のCCS・CCU・CCUS技術の取り組みは、政府、研究機関、民間企業が連携し、多岐にわたって進められています。以下に、主要な国内事例を詳しく解説します。
- CCS(CO2回収・貯留)の取り組み
- 苫小牧CCS実証試験:
- 日本で初めての大規模CCS実証試験として、北海道苫小牧市沖合で実施されました。
- 2016年からCO2の圧入を開始し、2019年には累計30万トンの圧入を達成しました。
- 現在は、貯留されたCO2のモニタリングや安全性評価が行われています。
- 日本CCS調査株式会社:
- 経済産業省の主導で設立された企業で、CCSの早期実現を目指し、技術開発や調査活動を行っています。
- CO2貯留に適した地層の調査や、CO2輸送技術の開発などに取り組んでいます。
- 大規模CCS実証事業:
- 2030年のCCS事業開始を目指して、日本各地で大規模なCCS実証事業が計画されています。
- CO2の分離・回収、輸送、貯留までの一連の技術の実証と、安全性の評価が行われます。
- CCU(CO2回収・利用)の取り組み
- メタネーション技術:
- CO2と水素を反応させ、都市ガスの主成分であるメタンを合成する技術です。
- 東京ガス、大阪ガスなどのエネルギー企業が、実用化に向けた研究開発を進めています。
- CO2を用いた化学品製造:
- CO2を原料として、プラスチックや化学品を製造する技術です。
- 三菱ケミカル、住友化学などの化学メーカーが、実用化に向けた研究開発を進めています。
- CO2を用いたコンクリート製造:
- CO2をコンクリートの製造過程で利用することで、CO2の固定化とコンクリートの強度向上を目指す技術です。
- 鹿島建設、大成建設などの建設会社が、実用化に向けた研究開発を進めています。
- 藻類によるCO2固定化:
- 佐賀県佐賀市では、日本で初めてごみ焼却場の廃棄物発電施設にCO2分離・回収設備を設置し、回収したCO2は藻類培養業者に売却され、化粧品やサプリメントとして製品化しています。
- CCUS(CO2回収・利用・貯留)の取り組み
- CCSとCCUを組み合わせたCCUS技術の開発も進められています。
- 例えば、CO2を回収して化学品や燃料に利用し、残りのCO2を地中貯留するなどの取り組みが行われています。
今後の展望
- 日本政府は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、CCS・CCU・CCUS技術の社会実装を加速化する方針です。
- 技術開発、コスト削減、法整備、国民理解の促進など、多岐にわたる取り組みを推進しています。
- 産学官連携を強化し、国際的な協力も進めながら、CCUS技術の発展を目指しています。
これらの取り組みを通じて、日本はCCS・CCU・CCUS技術の分野でリーダーシップを発揮し、地球温暖化対策に貢献することを目指しています。
2)海外:
海外におけるCCS・CCU・CCUS技術の取り組みは、地域や国の特性に応じて多様な展開を見せています。以下に、主要な事例をいくつか紹介します。
ノルウェー:スライプナープロジェクト
- ノルウェーは、世界で初めてCCSを商業規模で実現した国として知られています。
- 1996年に開始された「スライプナープロジェクト」では、天然ガス採掘時に発生するCO2を分離し、海底の帯水層に貯留しています。
- このプロジェクトは、CO2の長期安定貯留の可能性を示し、CCS技術の発展に大きく貢献しました。
アメリカ:エクソンモービル社の取り組み
- エクソンモービル社は、CCS技術の開発と実用化に積極的に取り組んでいます。
- 特に、テキサス州ヒューストン周辺での大規模なCCSプロジェクトを計画しており、年間数千万トンのCO2貯留を目指しています。
- このプロジェクトは、産業集積地におけるCO2排出削減のモデルケースとして注目されています。
アイスランド:カーボン・リサイクリング・インターナショナル
- アイスランドのカーボン・リサイクリング・インターナショナルは、CCU技術を活用し、CO2からメタノールを生産しています。
- 地熱発電によって得られる再生可能エネルギーとCO2を原料としており、持続可能な燃料生産の可能性を示しています。
- 同社はメタノール製造技術「Emissions-to-Liquids」を普及させています。
ヨーロッパ各国
- ヨーロッパでは、EUを中心にCCS・CCU・CCUS技術の推進が積極的に行われています。
- 特に、北海周辺では、CO2の越境輸送・貯留に関する協力が進んでおり、大規模なCCSインフラの構築が計画されています。
- ドイツの化学メーカーCovestro AG は、CO2とプロピレンオキシドを反応させてポリマー原料であるポリオールを生産しています。
中国
- 中国企業もカーボン・リサイクリング・インターナショナルから技術提供を受けメタノール生産を行っています。
これらの事例からわかるように、CCS・CCU・CCUS技術は、各国がそれぞれの資源や産業構造に合わせて、多様な形で展開されています。
CCS・CCU・CCUS技術は、地球温暖化対策と資源循環型社会の実現に向けた重要な鍵となります。日本を含む世界各国で技術開発と社会実装が進んでおり、今後の発展が期待されます。
