エコリクコラム
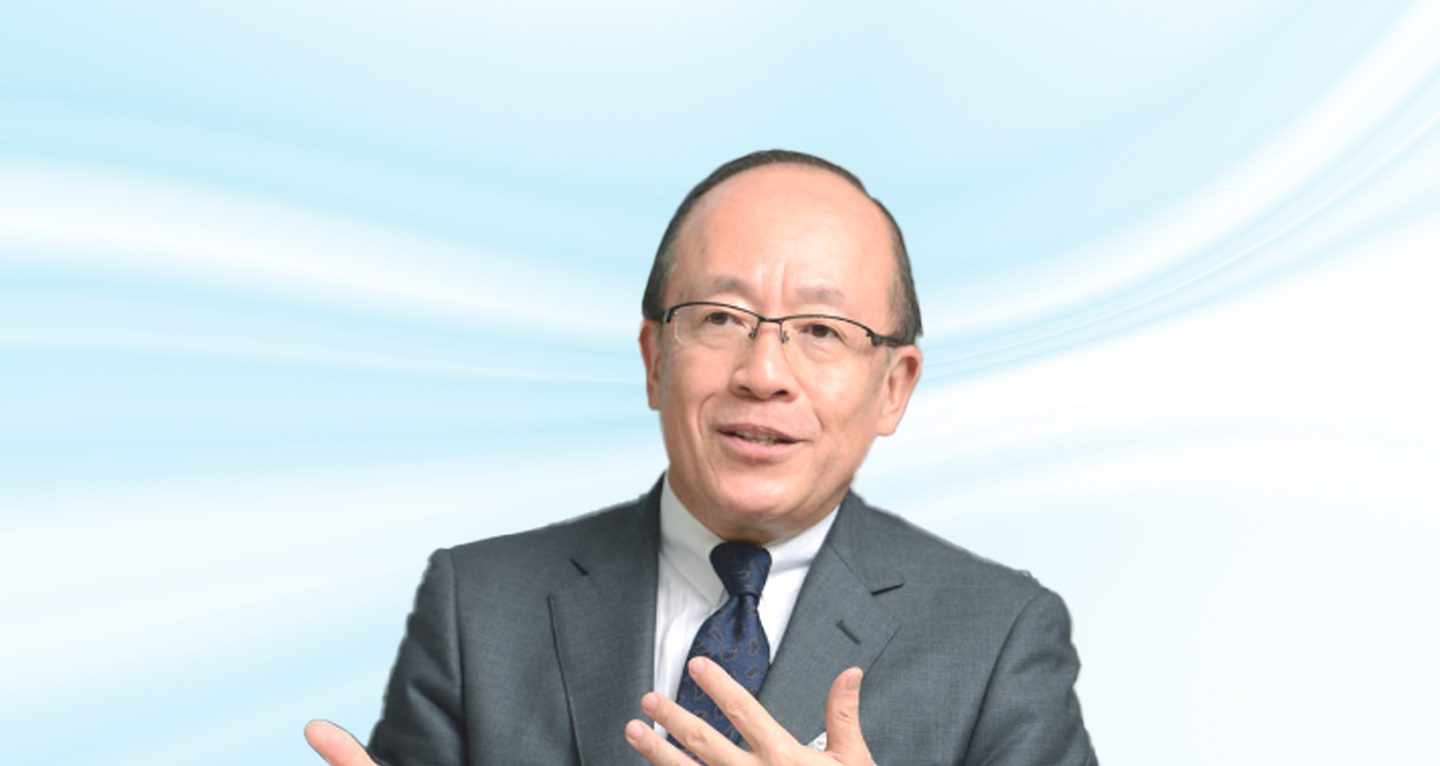
2025.4.21
インタビュー
元スクウェア・エニックス米社長 岡田大士郎氏に聞く
「わくわく」が人生を豊かにする。
「すべての人々が、社会でもっと喜びを感じながら働き暮らせる社会をつくり出す」
その壮大な目標を掲げ、株式会社HLD Labを設立した岡田大士郎氏。金融業界からゲーム業界という異色のキャリアを歩み、かつてはスクウェア・エニックスの米国法人社長として数々のヒットタイトルを世に送り出してきました。組織風土改革とウェル・ビーイング経営の先駆者としても知られる岡田氏は、スクウェア・エニックス時代にワークプレイス改革を主導し、従業員の創造性を最大限に引き出す環境づくりに尽力してこられました。現在は、その経験と知見を活かし、企業や教育機関に向けたコンサルティングや人材育成を通じて、「幸福社会」の実現に向けた活動を精力的に展開しています。今回は、サステナビリティ推進においても重要な視点となるワークライフバランス、そして私たちが「わくわく」しながら幸福な人生を送るためのヒントについて、岡田氏に深く掘り下げてお話を伺いました。
株式会社HLD Lab設立までの経緯:異質なキャリアと原体験が導いた「幸福」への探求
長年ゲーム業界の第一線で活躍されてきた岡田氏が、なぜ今、人々の幸福度向上に取り組む会社を設立されたのでしょうか。その背景には、ご自身のユニークなキャリアと、強い問題意識があったと言います。
「日本興業銀行(現みずほ銀行)に入行後、ロンドン勤務などを経て、ドイツ銀行グループでは国際税務統括責任者を務めてきました。グローバルな金融の世界でキャリアを積む中で、多様な価値観や働き方に触れることができました。しかし、外資系企業の厳しい人事政策を目の当たりにする中で、組織と個人の関係性について深く考えるようになりました。」
1999年、ドイツ銀行グループに移籍後、岡田氏は外資系企業のシビアな人事制度を経験。その中で、従来の金融業界的な価値観への疑問が芽生え、「もっと人が主体的に、喜びを感じながら働ける社会があるべきではないか」という強い思いを抱くようになったと言います。その後の企業再建の失敗経験も、画一的な組織運営ではなく、人的資本を重視する経営姿勢を確立する大きな転機となりました。
2005年、岡田氏はスクウェア・エニックスに転身。米国現地法人COO時代には、全社員との1対1の面談を徹底的に行い、組織の課題や個々の才能を深く理解することから改革をスタートさせました。ディズニーやルーカスアーツといったクリエイティブ企業のオフィス環境を視察するなど、エンターテインメント業界ならではの自由な発想を取り入れ、「人が心から楽しめること、夢中になれること」が組織の活性化に不可欠であることを確信しました。日本本社総務部長時代には、クリエイターの創造性を最大限に引き出す空間設計理論を確立し、本社移転プロジェクトを成功に導くなど、「働く場」のデザインが従業員の幸福度と生産性に大きく影響することを実証しました。

出所)三幸エステートHP「株式会社スクウェア・エニックス」(※1)
ゲームというエンターテインメントを通じて人々に感動を与えてきた経験、そして組織運営における成功と失敗の両方の経験を経て、岡田氏は「人が内発的なモチベーションを高め、主体的に幸福を感じられる社会の実現」こそが自身の使命だと強く感じるようになり、株式会社HLD Labの設立に至ったのです。
ウェル・ビーイングを高めるために必要な取り組み:主体的な「心の持ちよう」と「わくわく」できる場の創造
2024年3月に国連が公開した「世界幸福度報告」によると、日本の幸福度は143カ国中51位と、G7の中でイタリア(41位)に次いで最も低い結果となっています。この現状に対し、岡田氏は警鐘を鳴らします。
「この結果は、私たち日本社会全体が真剣に受け止めるべきだと思います。幸福度を高めるためには、社会全体の意識改革はもちろん、個々人の働き方や考え方を変えていく必要があります。」
数々の調査結果から、ウェル・ビーイングを高める重要な要素の一つとして、「家計満足度」や「人生における選択の自由」が挙げられると言います。しかし、岡田氏はそれらに加えて、より本質的な要素として「心の持ちよう」の重要性を強調します。これは、ESGにおけるS(社会)への対応、特に従業員のエンゲージメント向上や働きがいのある環境づくりに深く関連する視点です。
「やらされ感で仕事をするのではなく、『自分がやりたいからやる』という主体的な意識を持つことが大切です。そのためには、個人が自分の興味や強みを発揮できるような『場』の提供が不可欠です。会社であれば、社員一人ひとりの意見に耳を傾け、挑戦できる機会を与える。教育の現場であれば、生徒たちが自ら学びたいと思えるような魅力的な授業を展開する。そういった環境づくりが、結果的に個人のウェル・ビーイングを高め、ひいては社会全体の幸福度向上につながると信じています。」
スクウェア・エニックス時代、組織風土改革を主導した岡田氏の経験に基づけば、トップダウンの指示ではなく、従業員一人ひとりの個性や能力を尊重し、心理的安全性の高い環境で主体的な挑戦を促すことが、エンゲージメントを高める上で不可欠です。また、多様な意見が活発に交換されるオープンなコミュニケーションは、新たなアイデアの創出を促し、「わくわく」する気持ちを生み出す源泉となります。
HLD Labでは、企業や教育機関に対し、そうした「わくわく」できる場づくりを支援する様々なプログラムを提供しています。これらは、単なる福利厚生の充実ではなく、従業員の内発的なモチベーションを引き出し、組織全体の活性化に繋げるための戦略的な取り組みと言えるでしょう。
岡田氏が目指す世界を実現するために必要な人材とは:変革への意欲と共感力、そして柔軟な発想
岡田氏が思い描く、人々が喜びを感じながら働き暮らせる社会。その実現には、どのような人材が求められるのでしょうか。それは、社会が抱える課題を自分事として捉え、その解決に向けて主体的に行動できる人材と言えるでしょう。
「最も大切なのは、『現状維持は後退である』という危機感を持ち、常に新しいことに挑戦しようとする意欲のある人です。変化の激しい現代において、立ち止まっていることは衰退と同じです。常にアンテナを張り、新しい知識やスキルを学び続ける姿勢が重要です。そして、自分の周りの人たちの喜びを自分の喜びとして捉えられる、共感力の高い人も不可欠です。チームで仕事をする上で、他者の感情を理解し、協力し合うことは目標達成の原動力となります。」
岡田氏は、トップダウンで指示するのではなく、それぞれの個性や能力を尊重し、チームとして目標達成に向けて協力し合えるリーダーシップを発揮できる人材の育成も重要だと語ります。これは、従来の指示命令型のリーダーシップとは異なり、メンバーの主体性を引き出し、エンパワーメントする現代的なリーダーシップのあり方を示唆しています。 また、岡田氏は、既存の枠にとらわれない柔軟な発想を持つことの重要性も指摘します。
「過去の成功体験や固定観念に縛られず、『本当にこれでいいのか?もっと良い方法はないのか?』と常に問い続ける姿勢が大切です。そのためには、多様な価値観を受け入れ、積極的にコミュニケーションを取り、学び続けることが不可欠です。HLD Labでは、そうした考え方を広げ、実践できる人材育成にも力を入れていきたいと考えています。」
社会が抱える課題は複雑であり、単一の解決策では対応できないことが多くあります。だからこそ、多様な視点を取り入れ、対話を通じて新たな解決策を生み出す力が求められます。岡田氏が目指す社会の実現には、現状に満足せず、常に変革への意欲を持ち続け、他者への共感力と柔軟な発想を兼ね備えた人材が不可欠と言えるでしょう。
主体的な「わくわく」が拓く、幸福な未来への提言
インタビューを通して、岡田氏の言葉の端々から、人々への温かい眼差しと、より良い社会を築きたいという強い情熱が感じられました。「わくわく」する気持ちを大切にし、主体的に行動すること。それは、私たちが幸福な人生を送るための第一歩なのかもしれません。
元スクウェア・エニックス米社長という異色のキャリアを持つ岡田大士郎氏の挑戦は、私たち一人ひとりの働き方、生き方を改めて見つめ直すきっかけを与えてくれました。社会全体の幸福度を高めるためには、企業、教育機関、そして私たち一人ひとりが意識を変え、「わくわく」できる環境づくりと、主体的な行動を大切にしていく必要があるでしょう。岡田氏の提唱する「幸福働」の理念は、ESG経営においても、従業員のエンゲージメント向上という重要な側面を捉える上で、示唆に富むものと言えるのではないでしょうか。

